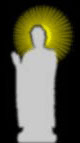其の八十一
【 清めの塩 】
『私の息子がケガレてるっていうの!!』
斎場(火葬場)のロビーに女性の凄まじい声が響いた。どうやら私たちより先に、どこか別の葬儀式場でお葬式を済ませて斎場についていた遺族のようだった。お葬式を執り行ったお婆ちゃんのお棺を炉に納めてから、斎場の係りの人に問いかけた。
『何かあったのですか?』
いぶかしげな顔で係りの男性が話した。
『ココであんなことする人、初めて見たわ!』
その横にいた女性の係りの人が呟いた。
『今、せんでもいいがに(しなくても良いのに)!』
事情はこうであった。
霊柩車が到着した。
車から棺が出され炉の前まで運ばれた。
棺にぴったりと寄り添う婦人の姿があった。
棺の中には十六歳の男の子が静かに横たわっていた。寄り添っていたのは母親だった。
読経が終わり棺は炉に納められた。
火葬時間の説明が終わり、係りの人が待合室に案内しようとしたその時、事件は起こった。
斎場に供して来ていた在所(村)の長老が、おもむろに、遺族を含めた参列者に『清めの塩』を配り始めた。それを見た母親は冒頭の言葉を叫んだ。
後で知ったことだが、十六歳の男の子の死因は、事故なのか、そうでないのかが判断しかねるものであった。母親の心中は深い悲しみの中で、さらに複雑な思いにさいなまされていたにちがいない。そして、幸か不幸か、このお母さんは『清めの塩』の『意味』を『知っていた』のである。確かに、知っていたなら、そう叫ばずにはいられなかったはずである。
『清めの塩』それは、死をケガレとして受け止める物の考え方に由来する。昔から殺菌作用があることが知られていた塩を用いて、ケガレを払うためにおこなう行為である。
死をケガレとする意識は、神道以前の日本的感覚に根源がある。「古事記」で、イザナギが黄泉の国で腐敗した妻の姿を見て逃げ帰った後、身体を海水でみそいだことがその始源とされている。
清めの塩を用いるようになったのは、江戸時代初期半ばより一般に広まった慣習であり、それまでは、酒、食事、つまり現代でいうところの会食をすることによってケガレを払っていた。
死をケガレとする考え方は、神道に強く現れている。ゆえに神道における葬送の義はお祓いをして、ケガレを祓い亡くなった人を送るのである。しかし、仏教において死はケガレではない。特に浄土真宗において死はケガレどころか尊ぶものである。死を、特別な忌み嫌い、畏れおののくものとはとらえず、生まれ死すというさけようのない『道理』とみるのである。
さらに、親しい縁ある人の死は、その『道理』を知らし示してくれたと受け止める。そこには、死をケガレたものという意識は、ただの一辺も存在しない。ゆえに、ケガレではない死を清める必要はなく、当然清めの塩を使うという行為は行わない。
冒頭の母親の言動は、当たり前とば当たり前なのである。しかし、一般に広がり、村という社会に根付いた慣習は、その行為が良い悪いではなく、なかなか無くならないのが現実である。そのことは、死をケガレ、忌み嫌うというものの考え方が無くならないということと等しいと言える。けれど…どんなに死をケガレとしてみても、忌み嫌っても、死はだれにでも必ず訪れる。
私たちは産まれ時から『限りある命』を生きている。致死率100%『死』から逃れられないのである。ならば、その『死』というものを嫌わず、逃げず(見ないようにしたり、考えないようにしたり)、きちんと背負って生きていかねばならないのではないだろうか。
死を見つめて、初めて、『生きる』ということが、見えてくるのだから…。
亡くなった人は、その自らの死をもって、娑婆に残った私たちに『生きている』という現実と『生きる』という姿勢を説いていてくれる。その説いに私たちは答えていかなければならないはずである。そうすることが、真の意味で死をケガレとしないと云うことなのである。
合掌
[2013/06]
追伸
金沢では、近年やっと、浄土真宗のお葬式において、『清めの塩』は使用しなくなって来ている。
小話のご意見・ご感想はこちらまでメールしてください。